# クオリティ・オブ・ソサエティ
# 問いという帆

クオリティ・オブ・ソサエティ――2020年以降の電通総研の活動とこれから
クオリティ・オブ・ソサエティ――2020年以降の電通総研の活動とこれから

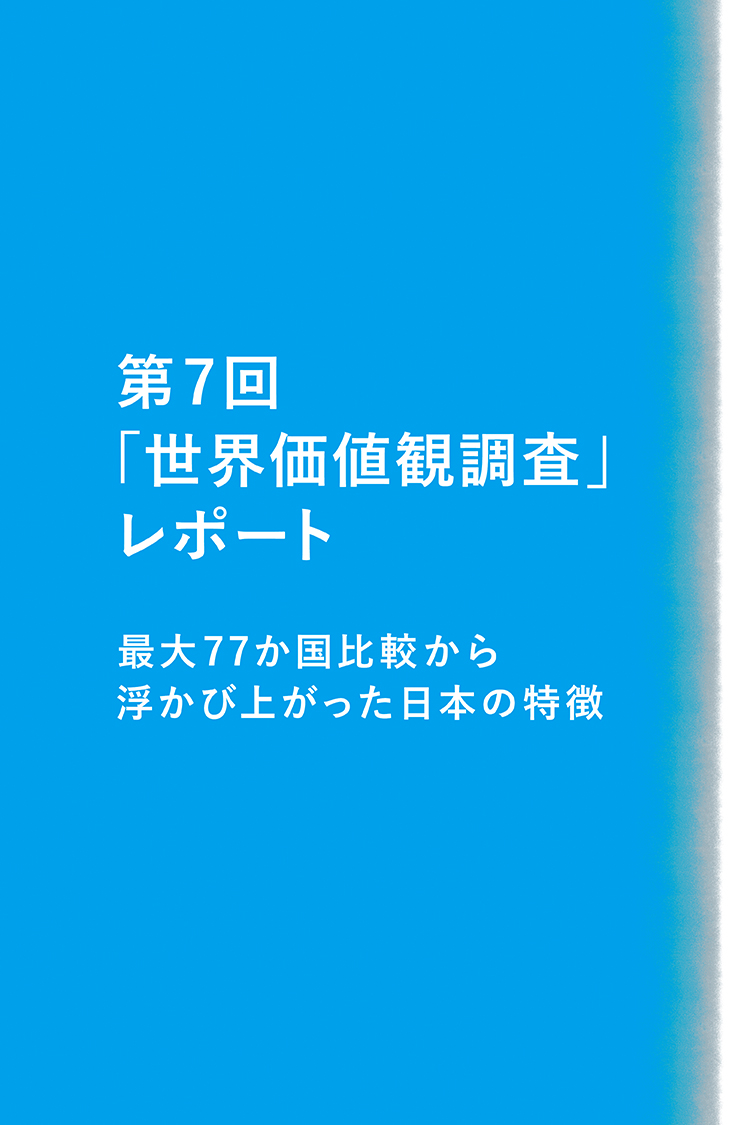
株式会社 電通グループ(本社:東京都港区、代表取締役社長執行役員:山本 敏博)の社内組織である電通総研(所長:谷 尚樹)と学校法人同志社 同志社大学(所在地:京都府京都市、学長:植木 朝子)のメディア・社会心理学研究分野の池田研究室※(教授:池田 謙一)は、延べ100以上の国と地域を対象にした「世界価値観調査」(WVS: World Values Survey)について独自に国際比較分析(協力:株式会社電通マクロミルインサイト)を行いました。その結果、日本の特徴として9つのことが浮かび上がりました。
世界価値観調査は、個人を対象に価値観を聞くもので、その設問の範囲は政治観、経済観、労働観、教育観、宗教観、家族観など290項目に及びます。同調査は1981年に開始され、電通総研は第2回調査(1990年)から参画しており、今回で7回目となりました。
第7回調査では、世界価値観調査 (WVS) とヨーロッパ価値観研究(EVS: European Values Study)の共同でデータセットが構築され、2017年から2021年にかけて実査が行われました。電通総研と同志社大学は、2020年9月時点で集計が終了している77か国を対象に国際比較分析を行い、日本の9つの特徴を導き出しました。なお、WVSとEVSで調査票が完全には同一ではないこと、ヨーロッパ以外であっても各国でカスタマイズしている設問があることから、設問により回答国数が異なるため、今回は45か国から77か国で集計可能な設問をランキング形式で分析しています。
今回の結果から見えてきたのは、日本の人びとは「仕事」よりも「余暇」を重視する一方で、「働くことがあまり大切でなくなる」ことは良しとしない。「政治」への関心は高いが話題にしない。「国家」に安心を求めるが「権威」を嫌う。「環境保護」か「経済成長」かと問われると、わからないとする人が多い。このように一見すると矛盾するような回答や、選択をせまられると逡巡してしまう傾向が随所にみられました。こうした葛藤の背景には、世界が大きく変化していることによる影響があります。
少子高齢化の加速はその一つで、調査結果を見ると、日本社会では「家族」を大切にしつつも、両親の長期介護への義務感は低い状況です。介護サービスが普及しているからかもしれませんが、そうした社会体制を維持できるかは日本の大きな課題の一つです。
一方で、次世代を担う子どもに身につけさせたい性質としては、勤勉さといった伝統的生活価値あるいは工業的価値よりも、創造性などの脱工業社会的な価値を優先させたいという、先を見据えた志向性が垣間見えます。矛盾や葛藤を抱えながらも、望ましい社会の構築に向け、人びとがどのような意識のもとで選択をしていくのか、他国と比較しながら今後も追い続ける必要があると考えています。
2020年はCOVID-19(新型コロナウィルス感染症)が世界的に広がりましたが、77か国のうち日本を含む66か国は2019年までに実査を終えているため、COVID-19今回の調査結果にあたえた影響は限定的と言えます。しかしCOVID-19に限らず、世界は大きな変動の中にあり、だからこそ長期にわたる世界的な意識調査は、変化を捉え、未来を描いていくうえで役立つものであると考えます。「人」の意識や価値観、行動の変容は、「社会」の質(“クオリティ・オブ・ソサエティ”)と密接な関係にあるからです。
◎プレスリリースはこちらをご参照ください。
第7回「世界価値観調査」リリース~分析から浮かび上がった“日本の9つの特徴”
◎レポ ート詳細はこちらからご参照ください。
第7回「世界価値観調査」レポート~最大77か国比較から浮かび上がった日本の特徴
◎国際比較ランキング詳細はこちらからご参照ください。
第7回「世界価値観調査」Appendix
※池田研究室について
組織名:同志社大学 社会学部 メディア学科 池田謙一研究室
代表者:教授 池田 謙一
研究内容:メディアコミュニケーション、政治社会心理学の再構成、社会のリアリティの社会心理学的研究URL:http://www.ikeken-lab.jp/
Text by 日塔 史

電通総研プロデューサー/研究員
山形県生まれ。2020年2月より電通総研。現在の活動テーマは「次世代メディアとコミュニケーション」。経済学・経営学のバックグラウンドと、マスメディア・デジタルメディア・テクノロジー開発での実務経験を活かして、マクロ視点からコミュニケーションのメガシフトを研究する。
山形県生まれ。2020年2月より電通総研。現在の活動テーマは「次世代メディアとコミュニケーション」。経済学・経営学のバックグラウンドと、マスメディア・デジタルメディア・テクノロジー開発での実務経験を活かして、マクロ視点からコミュニケーションのメガシフトを研究する。